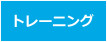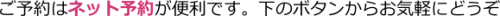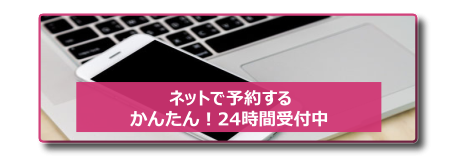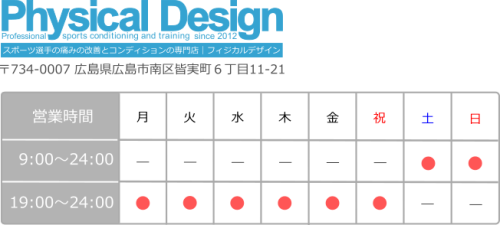広島で野球肩の痛みにお悩みの方へ 【完全ガイド】
フィジカルデザイン スポーツ整体 > スポーツの痛み > 広島で野球肩の痛みにお悩みの方へ【完全ガイド】
広島で野球肩の痛みを治したい方へ
はじめに
![]()
投球動作における肩の痛みを防ぐために
野球選手にとって「肩」は、パフォーマンスを左右する最も重要な場所のひとつです。
特にピッチャーをはじめ、日々の練習やトレーニングの中で投球動作を繰り返す選手ほど、肩への負担は蓄積しやすく、気づかないうちに痛みや違和感を抱えてしまうケースも少なくありません。その代表的な障害が「野球肩」です。
「病院や治療院に通ってもなかなか改善しない」
その原因の多くは、痛みの出ている肩だけに注目した対処に留まっていることにあります。野球肩を根本から改善し再発を防ぐためには、全身の関節の動き(可動域)を整えたうえで、投球動作そのものを見直すことが欠かせません。
当店は、短期間で野球肩を改善することに全力を注いでおり、広島カープをはじめとしたプロ野球投手、広島商業高校・新庄高校・崇徳高校・瀬戸内高校・国際学院高校・クラブチームなど、数多くの投手・捕手・野手の施術実績を有しています。
中四国・九州エリアのエース投手からも厚い信頼をいただいてきました。参考:お客様からのお声
このページでは、広島のスポーツ整体「フィジカルデザイン」に在籍する理学療法士監修のもと、野球肩の基礎知識から原因、予防、改善方法までを、専門的な内容をわかりやすく解説していきます。
肩の痛みで思い切り投げられない選手、競技復帰やパフォーマンス向上を目指す方は、ぜひご覧ください。
目次
• 野球肩の原因
• 野球肩の治療法
• 再発を防ぐ!予防とトレーニング法
• 保護者・指導者ができること
👉 まずは「野球肩の主な原因」から理解していきましょう。
野球肩の原因
![]()

「野球肩」と聞くと、まず「投げすぎ」が原因だと思うかもしれません。しかし、本当に重要な原因は 「複数の関節の動きが悪くなり」スムーズな投球が難しくなったことです。
特に、股関節・胸郭・肩甲骨の関節が動きにくくなると、全身を使った投球ができなくなり、「腕投げ」に頼って球速を上げようとしてしまいます。その結果、肩や肘に過剰な負担やストレスがかかりやすくなります。こうした状態の背景には、練習や筋力トレーニングによる疲労の蓄積に加え、日常的なケアやメンテナンス不足が関係しています。
一生懸命に練習をして疲労が蓄積
⇓
複数の関節の動きが悪くなってくる
⇓
適切なフォームが崩れる
⇓
肩への負担が大きくなる
⇓
肩が損傷し痛みが出る
このような流れで、肩に過剰な負担がかかるようになり、やがて慢性的な痛みにつながってしまうため、野球肩を防ぐにはこの悪い流れを起こさないように修正する必要があります。
野球肩につながる複数の原因
【1】関節可動域の低下
日頃の練習やトレーニングにより、股関節・肩甲骨・肩関節、そして胸まわりの関節が動きにくくなると、「肩や腕の力に頼る投球(腕投げ)」になりやすく、肩まわりの筋肉や腱に必要以上の負担がかかり痛みのリスクが高まります。
【2】体幹・股関節・肩甲骨の連動不足
関節の可動性が低下すると、インナーマッスルの働きが弱まり、身体の安定性が損なわれます。身体が不安定になると筋肉は硬くなり、下半身や体幹で生み出した力を腕へスムーズに伝えられなくなります。その結果、全身の連動が失われ、投球時に肩や腕へ過剰な負担がかかります。
【3】筋力のアンバランス
大胸筋など一部の筋肉だけを鍛えたり、練習やトレーニング後のストレッチを怠ると、姿勢が崩れてきます。その結果、関節の動きも悪くなり、体幹や大殿筋の機能が低下して、筋力を十分に発揮できなくなり、投球に肩・腕の過剰な力が必要となりストレスがかかります。
【4】投球フォームの乱れ
肘が下がってしまったり、腕投げになったり…。こうしたフォームの乱れは、関節可動域の低下、姿勢の崩れ、筋力のアンバランスなどの複合した要因で生じます。フォームが乱れると、肩以外の関節にも必要以上の負担がかかってしまい、腰痛など思わぬケガにつながる危険性が高くなります。
👉 詳しくはこちら:「【5】 投球フォームを「10フェーズ」で徹底解析! 野球肩・野球肘を予防する正しいメカニズム」をさらに詳しく見る
【5】オーバーユース(投げすぎ)
上記のような問題を残したまま投球を続けるということは、いつ肩の痛みが出てもおかしくない状態です。病院でオーバユース(投げすぎ)による野球肩と診断された方は、投げ続けれる全身状態ではなかったと言えるでしょう。
【6】成長期の選手
中学生や高校生など、まだ成長途中の選手は、投げ方の知識が十分でなかったり、骨や筋肉が発達途中であるため、無理がききにくい時期です。力まかせに強く投げ続けたり、ストレッチなどのケアを十分に行わず練習を重ねると、慢性的な疲労から「野球肩」が治りにくくなるリスクが高くなってしまいます。
まとめ:野球肩は「肩だけ」の問題ではない
野球肩は、単なる肩のトラブルではなく、全身の関節可動域の制限により、投球フォームが崩れた結果として起こる障害です。そのため、予防や改善のためには以下のポイントがとても重要になります
• 日々の可動域とフォームのチェック
• 投球技術の知識を学ぶ
• 可動域を改善するストレッチ・ケア
• 十分な休養と食事
こうした積み重ねが、ケガ無く野球を続けるための土台になり、安定した結果を出すことができます。「少し変だな」と異変を感じたら、早めの見直しが重要になります。
👉 詳しくはこちら:「【2】 野球肩の原因と悪化要因|投げすぎだけじゃない本当の理由」をさらに詳しく見る
野球肩の治療方法
![]()

野球肩は、適切な調整を行えば、再び投げられるようになるケガです。しかし、酷使した身体の関節可動域を改善するの大変です。またストレッチなどで「痛みが消えた = 完治」と思ってしまうのは危険です。
痛みが治まっても、可動域が十分に改善していなければ、以前の投球動作に戻りやすく再び痛みが出ることがあります。本当の意味で回復するには、痛みが引いたあとも全身の使い方や投げ方を見直して、再発を防ぐことがとても大切です。
【1】初期対応(急性期)
炎症や強い痛みが出ている段階では、まず肩への負担を減らすことが最優先になります。
• 投球時に痛みがあれば、投球を中止し、肩への負担を減らす
• 痛みを感じる練習や筋力トレーニングは中断する
• 練習を休めない場合、スポーツ整体の利用を検討する
この時期に無理をすると、回復が遅れるだけでなく、症状が慢性化してしまう恐れがあります。「ちょっと痛いけど大丈夫」と思わず、早めの対応が重要になります。
【2】医療機関での治療
強い痛み、痛みが治まらない、日常生活にも支障が出るという場合は、早めに整形外科などの専門医を受診しましょう。
• レントゲンやMRIなどの画像診断(肩の状態を正確にチェック)
• 理学療法士によるリハビリ(可動域の回復、ストレッチ指導など)
• 湿布、注射、抗炎症剤(必要に応じて)
骨や靭帯などの状態を正確に把握することで、より的確な治療が可能になります。
【3】スポーツ整体でのアプローチ(当店の取り組み)
当店では、「肩の痛みそのもの」だけに注目するのではなく、全身の動きのバランスや投球フォームの修正にも目を向けたサポートを行っています。なるべく早めに対応することで練習を行いながら改善することが可能です。
• 投球動作の分析を通じたフォームの確認
• 全身の可動域の改善を図る
• 体幹や股関節の連動性・安定性を図る
• 投球技術の確認・再構築
少しずつ全身の反応をみながら、再発予防とパフォーマンス向上を目指した段階的なプログラムを進めていきます。「肩だけ」ではなく、「なぜ肩に負担がかかってしまったのか?」という根本原因にアプローチしていきます。
投球復帰までの段階的なアプローチ(当店の取り組み)
野球肩の痛みから全力投球が行えるように戻すには、段階を追って全身を整えていくことが大切です。
【1】可動域の回復(最も重要)
投球動作を行うために必要な全身の可動域を獲得し、無理なく肩を動かせる状態にしていきます。
【2】安定性の再構築
体幹をはじめ、肩甲骨・股関節の安定性や各部の連動性を高め、肩に負担をかけない土台を作ります。
【3】投球動作の再教育
投球動作の知識を学びながら、フォームのクセや崩れを見直し、肩に負担のかからない投げ方を身につけます。
👉 詳しくはこちら:「【5】 投球フォームを「10フェーズ」で徹底解析! 野球肩・野球肘を予防する正しいメカニズム」
【4】投球再開
まずは軽めのキャッチボールから。徐々に強度や距離を戻していきます。
まとめ:早めの対応と正しい調整が重要
野球肩の改善には、「痛みがなくなる → 全力で投げられる → 再発を防ぐ」という一連の流れが大切です。肩に違和感や痛みを感じたら、我慢せず、できるだけ早く適切なケアを受けるようにしましょう。
そして何より大事なのは、「投げられる身体」を作っていくこと。焦らず丁寧に身体を整えることで、安心してマウンドに戻る日が近づきます。
👉 詳しくはこちら:「【3】 野球肩の治療|投げられる肩を取り戻すために」を詳しく見る
再発を防ぐ!予防とトレーニング法
![]()
野球肩を防ぐために大切なのは、肩以外の場所にも視野を広げていくことです。全身を効率よく使えるようになると、確実に肩への負担は軽減し、力強い投球感覚を身につけていくことができます。
腕ばかりに頼った投球は、肩への負担が集中してしまいます。しかし、肩甲骨・体幹・股関節がしっかり連動して動いていれば、疲れにくい安定したフォームになり、ケガのリスクも大幅に減らすことができます。
効果的な予防トレーニング
日々の練習やトレーニングに、次のようなメニューを取り入れてみましょう。全身の連動性や肩の安定性を高めるのに役立ちます。
【1】胸郭・肩甲骨・体幹・股関節ストレッチ
投球を行うための土台となる体幹・肩甲骨・股関節の全可動域をスムーズに動かせるよう、回旋動作も加えながら可動性と安定性をアップさせていきます。
【2】股関節と体幹との連動
体幹を安定させながら股関節を使うようなトレーニングを取り入れると、下半身の力を効率よく上半身に伝えられるようになります。
【3】肩のインナーマッスルの機能改善
ゴムチューブなど非常に軽い負荷を用いて肩のインナーマッスル(回旋筋)に刺激を加えることで、肩の関節がしっかり安定し投球動作が楽になります。
【4】体幹の機能改善
腹圧を意識したエクササイズやバランスを保つ動きで、投球時の姿勢や出力を安定させることができます。
チーム全体で取り組む「予防の習慣化」
個人でのトレーニングも大切ですが、チームとして意識して取り組むことで、予防効果はさらに高まります。
【1】投球数・登板間隔の管理
練習においても長時間、同じ練習を続けるのを回避して投げすぎを防ぎ、肩に疲労がたまらないように調整しましょう。
【2】練習前後の可動域・フォームチェック
疲労やフォームの乱れに気づくことができれば、早めに対応していくことができます。
【3】定期的な身体チェック
可動域の変化や動作をチェックし、ケガの予兆を見逃さないようにします。
継続こそ、最大の予防
どんなに効果的なトレーニングや対策も、続けなければ意味がありません。日々の小さな積み重ねが、野球肩の再発を防ぎ、パフォーマンスの向上にもつながっていきます。「肩を守る」だけではなく、「思いきり投げられる身体をつくる」ことを目指して、ぜひ取り組んでみてください。
👉 詳しくはこちら:「【4】 野球肩の予防とトレーニング法|再発を防ぐ体の使い方」を詳しく見る
保護者・指導者ができること
![]()

保護者・指導者にできるサポートとは?
中学生や高校生など、成長期の選手たちは、身体も心もまだ発展途上です。この時期に起こるケガは、場合によっては将来の野球人生に大きく影響を及ぼすこともあります。だからこそ、保護者や指導者のサポートがとても大切です。子どもたちが長く野球を楽しめるように、私たち大人ができることをみていきましょう。
保護者ができるサポート
【1】小さなサインを見逃さない
「ちょっと痛いかも」「なんか違和感がある」そんな何気ない一言を、見過ごさないことが大事です。特に我慢強い子ほど、自分からは言い出しにくいこともあります。日頃からよく観察して、少しの変化に気づいてあげることが早期解決につながります。
【2】勝ち負けより、体を大事にする判断を
大事な試合や大会があると、つい無理をさせたくなる気持ちもあるかもしれません。しかし、不調がある時には、今は無理をさせない勇気こそが、未来のパフォーマンスを守ることになります。
【3】栄養・睡眠・回復を支える環境づくり
毎日の食事や睡眠、練習後の入浴やストレッチなど、回復のための習慣づくりも、保護者の大切な役割です。「しっかり食べて、よく寝る、毎日のストレッチ」当たり前のことが、実は一番の予防になります。
指導者ができるサポート
【1】投球数・登板間隔の管理
成長期の選手は、疲労の回復が大人より遅いと言われることもあります。だからこそ、投げすぎを防ぐ配慮やスケジュール管理がとても大切です。
投球制限の目安
小学生:週に約200球
中学生:週に約350球
高校生:週に約500球
【2】投球フォームのチェックと指導
フォームの乱れは、肩への負担を大きくする原因になります。定期的に投球フォームをチェックして、必要なときに正してあげることが、予防につながります。
【3】ウォーミングアップ・クールダウンの徹底
練習や試合前後の準備運動・整理運動は、ケガの予防に直結します。チーム全体でウォーミングアップとクールダウンを習慣化していきましょう。
まとめ:子どもたちの未来を守るために
野球肩の予防は、選手本人の努力だけでは限界があります。周囲の大人たちができるのは、「気づいてあげる」「声をかける」「無理をさせない」こと。それだけでも、子どもたちのケガはグッと減らせます。
小さなサインを見逃さず、長く・楽しく・健康に野球が続けられる環境を、私たち大人が一緒につくっていきましょう。
👉 詳しくはこちら:「【4】 野球肩の予防とトレーニング法|再発を防ぐ体の使い方」を詳しく見る
まとめ
![]()

野球肩は、決して“治らないケガ”ではありません。
早期の対処と、体の使い方の根本的な改善によって、再び全力でプレーすることは十分可能です。
痛みが続く場合、投球困難になる前の段階でスポーツ治療の専門家に相談してみましょう。
また、再発を防ぐには、体幹・肩甲骨・股関節の可動域と連動が重要。継続的なケアとトレーニングが、パフォーマンス向上にもつながります。
身体を正しく使えるようになれば、ケガを防ぐだけでなく、投球のキレや安定感も向上します。“投げ続けられる身体”をつくるために、日々の意識と取り組みが大切です。
👉 各詳細ページで、「原因」「治療」「予防」をさらに詳しく学びましょう。
【1】 野球肩の症状と見分け方|痛みが出る場所による症状の違いを徹底解説
【2】 野球肩の原因と悪化要因|投げすぎだけじゃない本当の理由
【3】 野球肩の治療とリハビリ|投げられる肩を取り戻すために
【5】 投球フォームを「10フェーズ」で徹底解析! 野球肩・野球肘を予防する正しいメカニズム
【6】野球肩がなぜ治らない?|痛みが続く本当の原因と正しい改善への道
スポーツ整体で痛みを改善し、最高のパフォーマンスを発揮しよう
![]()

競技力向上に向けたフィジカルデザインのサポート
あなたの競技力を最大限に引き出すために、フィジカルデザインは全力でサポートします。痛みを改善し、理想的なコンディションを手に入れるために、今すぐご予約をお待ちしております。
広島でスポーツの痛み改善・パフォーマンス向上なら
フィジカルデザインにお任せください!

 LINEからの問い合わせも可能
LINEからの問い合わせも可能
友達追加お願いします